
白内障とは?進行性の目の疾患について理解しよう
白内障は、目の中でレンズの役割を果たす水晶体が濁ってしまう疾患です。この濁りによって、光が網膜に正しく届かなくなり、視界がかすんだり、ぼやけたりするようになります。
私たちの目の水晶体は本来透明で、カメラのレンズのように光を屈折させ、網膜上に鮮明な像を結ぶ役割を担っています。しかし加齢などの原因により、水晶体のタンパク質が変性して濁りが生じると、その機能が低下してしまうのです。
白内障は50代で約半数、80代ではほとんどの方が経験する非常に一般的な眼の疾患です。進行すると日常生活に大きな支障をきたすこともありますが、早期発見と適切な対処により、視力低下の進行を遅らせたり、手術によって視力を回復させたりすることが可能です。
白内障は進行性の疾患であり、時間の経過とともに症状が悪化していきます。初期段階では気づきにくいこともありますが、進行するにつれて様々なサインが現れるようになります。

白内障進行の主なサイン10個
白内障の進行を示すサインは様々です。以下に主な10個のサインをご紹介します。これらの症状に心当たりがある場合は、早めに眼科医の診察を受けることをお勧めします。
白内障は初期段階では自覚症状がほとんどないことが多いのですが、進行するにつれて日常生活に影響を及ぼすようになります。早期発見が視力維持の鍵となりますので、定期的な眼科検診を受けることが重要です。
1. 視界のかすみや霧がかかったような感覚
白内障の最も一般的なサインは、視界全体がかすんだり、霧がかかったように見える症状です。これは水晶体の濁りによって、光が正しく屈折せず、網膜に鮮明な像を結べなくなるために起こります。
まるで曇りガラスを通して世界を見ているような感覚で、初期段階では気づきにくいこともありますが、徐々に進行していくと日常生活に支障をきたすようになります。特に読書や運転など、細かいものを見る必要がある作業で不便さを感じるようになるでしょう。
2. 光に対する過敏さ(まぶしさの増加)
水晶体が濁ると、入ってきた光が乱反射して散乱するため、まぶしさを強く感じるようになります。特に夜間の運転中に対向車のヘッドライトや街灯を見たときに、強いまぶしさや光の周りにハローと呼ばれる輪が見えることがあります。
この症状は皮質白内障や後嚢下白内障で特に顕著に現れます。水晶体が白く濁ることで光の散乱が生じやすくなり、日常生活での不便さや危険につながることもあるのです。
まぶしさが強くなると、屋外での活動が制限されたり、夜間の運転に不安を感じたりするようになります。このような症状が現れたら、早めに眼科を受診しましょう。
3. 色の認識力の低下
白内障が進行すると、色の見え方にも変化が生じます。特に核白内障では、水晶体の中心部(核)が黄色やオレンジ色に変色するため、青や紫などの色が識別しにくくなります。
まるで黄色いフィルターを通して世界を見ているような状態になり、色の鮮やかさが失われたり、似た色の区別が難しくなったりします。例えば、紺色と黒色の区別がつきにくくなるといった症状が現れます。
色の認識力の低下は、ファッションや芸術活動、交通信号の識別など、日常生活の様々な場面で影響を及ぼす可能性があります。
4. 夜間視力の著しい低下
白内障によって水晶体が濁ると、暗い環境での視力が特に低下します。これは、少ない光量の中でも正確に物を見るためには、水晶体の透明度が重要だからです。
夜間や薄暗い場所での視力低下は、日常生活における安全面でも大きな問題となります。階段の昇り降りが怖くなったり、夜間の運転に不安を感じたりするようになるでしょう。
この症状は白内障の進行とともに悪化していくため、早期の対処が重要です。夜間の視力に不安を感じるようになったら、眼科医に相談することをお勧めします。
5. 近視の進行(老眼との違い)
白内障の一種である核白内障では、水晶体の屈折率が変化することで一時的に近視が進行することがあります。これは「第二の近視」とも呼ばれ、老眼とは異なる現象です。
長年使っていた老眼鏡が合わなくなり、近くのものが見やすくなったように感じることもあります。しかし、これは視力が回復したわけではなく、白内障による屈折率の変化が原因です。
一時的に読書などが楽になったと喜ぶ方もいますが、この変化は白内障の進行を示すサインであり、放置すると視力はさらに低下していきます。眼鏡の度数が頻繁に変わるようになったら、白内障を疑う必要があります。
6. 単一光源が複数に見える(一つの光が二重三重に)
白内障が進行すると、一つの光源が二重、三重に見える「複視」という症状が現れることがあります。これは水晶体の濁りが不均一になり、光が複数の方向に屈折することで起こります。
例えば、月や街灯を見たときに、本来一つであるはずの光源が複数に分かれて見えるといった現象です。この症状は特に夜間に顕著になり、運転などの日常活動に支障をきたす可能性があります。
複視は白内障以外の眼疾患でも起こりうるため、このような症状が現れたら早めに眼科を受診して、原因を特定することが重要です。
7. 頻繁な眼鏡処方の変更が必要になる
白内障が進行すると、水晶体の屈折率が変化するため、短期間で眼鏡の度数が合わなくなることがあります。数か月ごとに眼鏡の処方を変更する必要が生じるのは、白内障進行の重要なサインです。
通常、眼鏡の処方は1〜2年程度は安定していますが、白内障が進行している場合は、新しい眼鏡を作っても数か月で見えにくくなってしまうことがあります。このような状況では、眼鏡の度数を頻繁に変更するよりも、白内障自体の治療を検討すべき時期かもしれません。
眼鏡の度数が安定しないと感じたら、白内障の可能性について眼科医に相談してみましょう。
8. 読書や細かい作業の困難さ
白内障が進行すると、新聞や本などの小さな文字を読むことが難しくなります。これは水晶体の濁りによってコントラスト感度が低下し、背景と文字の区別がつきにくくなるためです。
特に薄い色の文字や低コントラストの文字は読みづらくなり、読書や細かい手芸、料理など、精密な作業に支障をきたすようになります。明るい場所でも文字が見えにくい場合は、白内障が進行している可能性があります。
このような症状が現れたら、適切な照明を使用するなどの工夫をしながら、早めに眼科を受診することをお勧めします。
9. 視界の一部に固定された暗い影
白内障が特定の部位に集中して発生すると、視界の一部に常に暗い影や斑点が見えることがあります。これは水晶体の濁りが不均一に分布しているために起こる現象です。
この症状は網膜剥離などの他の眼疾患でも起こりうるため、突然視界に固定された影や斑点が現れた場合は、緊急の眼科受診が必要です。特に閃光や光の点滅を伴う場合は、網膜の問題である可能性が高いため、速やかに専門医の診察を受けてください。
視界の異常は見過ごさず、早期に適切な診断と治療を受けることが重要です。
10. 顔の認識や表情の読み取りの困難さ
白内障が進行すると、人の顔の細部や表情を認識することが難しくなります。これはコントラスト感度の低下と視力の全体的な低下によるものです。
知人に会っても顔がはっきり見えず、誰だかわからないという経験をしたことはありませんか?このような症状は社会生活にも影響を及ぼし、コミュニケーションの障壁となることがあります。
顔の認識が難しくなると、人混みでの不安や社会的な孤立感を感じることもあります。このような変化に気づいたら、眼科医に相談することをお勧めします。

白内障の種類と特徴的な症状
白内障には発生する場所によって異なる種類があり、それぞれ特徴的な症状を示します。主な種類とその症状について解説します。
白内障の種類を理解することで、自分がどのタイプの白内障を発症している可能性があるのか、また、どのような症状に注意すべきかがわかります。早期発見のためにも、これらの特徴を知っておくことは重要です。
皮質白内障の特徴と見え方
皮質白内障は、水晶体の外側にある皮質部分が白く濁る白内障です。水晶体の周辺部からくさび状に濁りが始まり、徐々に中心に向かって進行していきます。
皮質白内障の特徴的な症状は、光がまぶしく感じられることです。水晶体の周りが濁ることで光が乱反射し、特に夜間の運転中に対向車のヘッドライトや街灯を見たときに強いまぶしさを感じます。
また、コントラストが低い文字が読みにくくなるため、薄い色の文字や背景との区別がつきにくい文字の判読が困難になります。月を見たときに周りがぼやけたり、月が二重三重に見えたりすることもあります。
核白内障の特徴と色覚への影響
核白内障は、水晶体の中心部(核)が硬くなり、黄色やオレンジ色に変色する白内障です。この変色により、世界が黄色やオレンジ色のフィルターを通して見えるようになります。
核白内障の最も特徴的な症状は、色の見え方の変化です。特に青や紫などの色が識別しにくくなり、紺と黒など似た色の区別が難しくなります。また、水晶体の屈折率が変化することで一時的に近視が進行し、近くのものが見やすくなることもあります。
色の変化は徐々に進行するため、自分では気づきにくいことがあります。定期的な眼科検診で早期に発見することが重要です。
後嚢下白内障の早期症状と進行の特徴
後嚢下白内障は、水晶体の後ろ側の嚢(のう)の下に濁りが生じる白内障です。他の種類と比べて進行が早く、早期から視力低下を感じやすいのが特徴です。
後嚢下白内障の特徴的な症状は、読書など近距離での作業が困難になることです。また、まぶしさを強く感じたり、コントラスト感度が低下したりします。
この種類の白内障はステロイド薬の長期使用や糖尿病、放射線被曝などが原因で発症することが多く、若い年齢でも起こりうるため注意が必要です。ステロイド薬による白内障は発症すると進行が早く、数ヶ月から1年程度で手術が必要になるほど視力が低下することがあります。

白内障の主な原因と危険因子
白内障の発症には様々な要因が関わっています。最大の要因は加齢ですが、それ以外にも生活習慣や環境要因、全身疾患などが影響します。これらの原因を理解することで、予防や早期発見につなげることができます。
白内障は避けられない老化現象の一つと考えられがちですが、発症や進行に影響を与える因子を知り、適切に対処することで、その進行を遅らせることが可能です。
加齢による自然な変化
白内障の最も一般的な原因は加齢です。年齢を重ねるにつれて、水晶体のタンパク質が変性し、濁りが生じやすくなります。50代では約半数、80代ではほとんどの方が何らかの白内障を発症するとされています。
加齢による白内障は避けられない面もありますが、定期的な眼科検診を受けることで早期発見・早期治療が可能です。また、生活習慣の改善や紫外線対策などにより、進行を遅らせることができる場合もあります。
加齢性白内障は通常、両眼に発症しますが、進行の度合いは左右で異なることがあります。一方の目の視力が良好であれば、もう一方の視力低下に気づきにくいこともあるため、定期的な検査が重要です。
紫外線と放射線の影響
紫外線の長期的な曝露は白内障のリスクを高めることが知られています。特に紫外線の強い熱帯や亜熱帯地域の住民、屋外労働者、屋外スポーツを頻繁に行う人などは、白内障のリスクが高まります。
放射線も水晶体に障害を与え、白内障の原因となります。原爆被爆者やチェルノブイリ原発事故の作業者、医療従事者や宇宙飛行士など職業的に放射線に曝露する機会の多い人々では、白内障の発症率が高いことが報告されています。
紫外線から目を守るためには、紫外線カット機能付きのサングラスや眼鏡、コンタクトレンズの使用が効果的です。また、つばの広い帽子をかぶることも補助的な対策となります。
糖尿病とステロイド薬の影響
糖尿病は白内障の重要なリスク因子です。糖尿病患者は健常者に比べて約5倍白内障になりやすいとされており、特に60歳以下の若年層や女性でその影響が顕著です。
また、ステロイド薬の長期使用も白内障の原因となります。特に内服薬や吸入薬として使用される全身性ステロイドは、後嚢下白内障を引き起こすリスクが高いです。ステロイドによる白内障は進行が早く、数ヶ月から1年程度で手術が必要になるほど視力が低下することがあります。
糖尿病患者やステロイド薬を使用している方は、定期的な眼科検診が特に重要です。早期発見により適切な対処が可能となります。
専門医が勧める白内障への対処法
白内障の症状に気づいたら、どのように対処すべきでしょうか。初期段階から進行期まで、状態に応じた適切な対応が重要です。ここでは、眼科専門医として多くの白内障患者を診てきた経験から、効果的な対処法をご紹介します。
白内障は進行性の疾患ですが、適切な対処により視力低下の進行を遅らせたり、手術によって視力を回復させたりすることが可能です。症状の程度に合わせた対応を心がけましょう。
初期症状への対応と生活の工夫
白内障の初期段階では、生活の中での工夫によって不便さを軽減することができます。まず、適切な照明を確保することが重要です。明るすぎず暗すぎない、グレアの少ない照明環境を整えましょう。
読書や細かい作業をする際には、拡大鏡や老眼鏡を活用すると見やすくなります。また、コントラストを高めるために、白い紙に黒い文字の本や、背景と文字のコントラストが高い電子書籍リーダーを使用するのも効果的です。
屋外では、紫外線カット機能付きのサングラスや帽子を着用して、紫外線から目を守りましょう。これは白内障の進行を遅らせるだけでなく、目の健康全般に良い影響を与えます。
定期的な眼科検診の重要性
白内障の早期発見と適切な管理のためには、定期的な眼科検診が不可欠です。40歳を過ぎたら、症状がなくても2年に1回程度の眼科検診をお勧めします。糖尿病や家族歴がある方は、より頻繁な検診が必要です。
眼科検診では、細隙灯顕微鏡という特殊な機器を用いて水晶体の状態を詳細に観察し、白内障の有無や進行度を評価します。また、視力検査や眼圧測定なども行い、総合的に目の健康状態をチェックします。
定期的な検診により、白内障の進行を早期に発見し、適切な時期に治療を開始することができます。また、白内障以外の眼疾患も同時にチェックできるため、目の健康維持に役立ちます。
手術のタイミングと最新の治療法
白内障の根本的な治療法は手術です。現在の白内障手術は技術の進歩により、日帰りで行える安全で効果的な治療となっています。では、手術を受けるべきタイミングはいつでしょうか?
基本的には、白内障による視力低下が日常生活に支障をきたすようになったときが手術を検討するタイミングです。例えば、趣味や仕事に支障が出る、夜間の運転に不安を感じる、読書や細かい作業が困難になるなどの状況が当てはまります。
現代の白内障手術は、濁った水晶体を超音波で砕いて吸引し、代わりに人工の眼内レンズを挿入する「超音波乳化吸引術」が主流です。手術時間は通常10〜15分程度で、局所麻酔で行われるため痛みはほとんどありません。
また、多焦点眼内レンズや乱視矯正レンズなど、様々な種類の眼内レンズが開発されており、患者さんの生活スタイルや希望に合わせた選択が可能になっています。手術前の詳細な検査と丁寧なカウンセリングにより、最適なレンズを選択することが重要です。
白内障と認知症の意外な関係
白内障と認知症には、一見すると関連がないように思えるかもしれませんが、実は密接な関係があることが近年の研究で明らかになってきています。視覚情報の低下が脳機能に与える影響について考えてみましょう。
私たちが日常生活で得る情報の約8割は視覚から入ってくると言われています。白内障によって視力が低下すると、脳に送られる情報量が減少し、それが認知機能に影響を及ぼす可能性があるのです。
視覚情報の低下が脳に与える影響
白内障により視界が霞んだり、コントラスト感度が低下したりすると、周囲の環境からの視覚情報が減少します。これにより、脳への刺激が減り、認知機能の低下につながる可能性があります。
特に高齢者の場合、視力低下によって読書や社会活動への参加が制限されると、脳への刺激がさらに減少し、認知機能の低下リスクが高まることが研究で示されています。また、視力低下によって身体活動が減少することも、認知機能に悪影響を及ぼす要因となります。
白内障手術によって視力が回復すると、脳への視覚情報入力が増加し、認知機能の改善につながる可能性があることも報告されています。視覚と認知機能は密接に関連しているのです。
白内障手術後の認知機能改善の可能性
興味深いことに、白内障手術を受けた高齢者の中には、手術後に認知機能が改善したケースが報告されています。これは、視力の回復によって脳への視覚情報入力が増加し、脳の活性化につながったためと考えられています。
また、視力が回復することで社会活動への参加が増え、他者とのコミュニケーションが活発になることも、認知機能の維持・改善に寄与すると考えられています。さらに、視力回復により身体活動量が増加することも、認知機能にポジティブな影響を与える要因です。
白内障手術は単に視力を回復させるだけでなく、認知機能の維持・改善にも貢献する可能性があるのです。高齢者の生活の質を総合的に向上させる観点からも、適切な時期の白内障治療は重要と言えるでしょう。
まとめ:白内障と上手に付き合うために
白内障は加齢とともに誰にでも起こりうる眼の疾患ですが、早期発見と適切な対処により、その影響を最小限に抑えることができます。この記事でご紹介した10個のサインに心当たりがある場合は、早めに眼科医の診察を受けることをお勧めします。
白内障の進行は個人差が大きく、症状の現れ方も様々です。定期的な眼科検診を受けることで、自分では気づきにくい初期の変化も発見することができます。特に40歳を過ぎたら、症状がなくても2年に1回程度の眼科検診を心がけましょう。
現代の白内障治療は非常に進歩しており、日帰り手術で安全に視力を回復させることが可能です。手術のタイミングは、日常生活に支障をきたすようになった時が一つの目安となりますが、個々の状況に応じて眼科医と相談しながら決めることが大切です。
また、白内障の予防や進行を遅らせるためには、紫外線対策や健康的な生活習慣の維持も重要です。サングラスや帽子の着用、バランスの良い食事、禁煙などを心がけましょう。
目の健康は全身の健康や生活の質と密接に関連しています。白内障の症状に早めに気づき、適切に対処することで、いつまでも明るく鮮やかな世界を見続けることができるでしょう。
白内障でお悩みの方は、専門医による適切な診断と治療を受けることをお勧めします。南船橋眼科では、最新の設備と豊富な経験を持つ医師が、患者さん一人ひとりに合わせた最適な治療をご提案しています。土日祝日も診療を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
詳しい情報や予約方法については、南船橋眼科の公式サイトをご覧ください。あなたの大切な目の健康をサポートいたします。
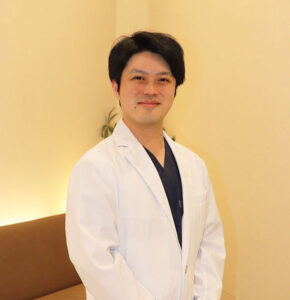
経歴
- 筑波大学医学群医学類 卒業
- 東京都立多摩総合医療センター 臨床研修医
- 東京医科歯科大学医学部附属病院 眼科
- 東京都保健医療公社大久保病院 眼科
- 川口市立医療センター 眼科
- 川口工業総合病院 眼科
- 柏厚生総合病院 眼科
- 南船橋眼科 院長








