
目次
白内障手術の基本と費用が気になる理由
白内障は加齢とともに発症率が高まる目の病気です。厚生科学研究班の報告によると、50歳代で37~54%、60歳代で66~83%、70歳代で84~97%、そして80歳以上では実に100%の方が何らかの白内障の症状を持っているとされています。
目がかすむ、まぶしく感じる、メガネが合わなくなった—こうした症状に心当たりはありませんか?
白内障は放置すると視力低下が進行し、日常生活に大きな支障をきたします。手術による治療が効果的ですが、多くの患者さんが「費用はどれくらいかかるのか」「保険は適用されるのか」という不安を抱えています。
実際、白内障手術の費用は使用するレンズの種類や手術方法によって大きく変わります。保険適用の有無も重要なポイントです。
この記事では、白内障手術の費用相場と保険適用の仕組みについて、眼科専門医の立場から詳しく解説します。手術を検討されている方やご家族の方が、経済的な不安なく最適な治療選択ができるよう、必要な情報をお届けします。
白内障手術の種類と費用の違い
白内障手術には大きく分けて3つのパターンがあります。それぞれ使用するレンズの種類や手術方法によって費用が異なりますので、まずはその違いを理解しましょう。
最も重要なのは、使用する眼内レンズの種類です。単焦点レンズと多焦点レンズでは、見え方だけでなく費用にも大きな差が生じます。
1. 単焦点眼内レンズを用いた保険診療
単焦点眼内レンズは、一つの距離(近くか遠く)にのみピントが合うレンズです。保険診療で使用される標準的なレンズで、費用は比較的抑えられています。
保険適用の場合の自己負担額は以下のようになります。
- 1割負担の方:片目 約15,000円 / 両目 約30,000円
- 2割負担の方:片目 約30,000円 / 両目 約60,000円
- 3割負担の方:片目 約45,000円 / 両目 約90,000円
単焦点レンズは保険適用なので費用負担は少なめですが、手術後も状況に応じて眼鏡が必要になる場合があります。遠くを見るためのレンズを選んだ場合は近くを見るときに、近くを見るためのレンズを選んだ場合は遠くを見るときに、それぞれ眼鏡が必要になるでしょう。
2. 多焦点眼内レンズを用いた選定療養
多焦点眼内レンズは、遠近両方の距離にピントを合わせることができるレンズです。2020年4月からは「選定療養」という制度が導入され、手術費用の一部に保険が適用されるようになりました。
選定療養とは、患者さんが追加費用を負担することで、保険適用外の治療を保険適用の治療と併せて受けることができる医療制度です。
費用の目安は以下のようになります。
- 手術代:約45,000円(3割負担の場合)
- レンズ代:約300,000円(自費)
- 合計:約345,000円(片目)
多焦点レンズは遠近両用なので、日常生活での眼鏡依存度が低くなるメリットがあります。ただし、単焦点レンズと比べると見え方の鮮明さが若干劣ることや、光がにじんで見える「グレア」や光の周りに輪っかが見える「ハロー」といった現象が生じる場合があります。
3. 多焦点眼内レンズを用いた自由診療
選定療養を導入していない医療機関では、多焦点眼内レンズを用いた手術は完全な自由診療(保険適用外)となります。この場合、手術費用もレンズ代も全額自己負担となります。
費用の目安は以下のようになります。
- 片目:約50万円~100万円
- 両目:約100万円~200万円
自由診療の場合、高額療養費制度は適用されませんが、医療費控除の対象にはなります。
保険適用の条件と範囲
白内障手術の保険適用には一定の条件があります。どのような場合に保険が適用され、どこまでが保険でカバーされるのか、詳しく見ていきましょう。
白内障手術の保険適用は、使用するレンズの種類によって大きく左右されます。
単焦点眼内レンズは全て保険適用
単焦点眼内レンズを使用した白内障手術は、すべて健康保険の適用対象です。検査費用、手術費用、入院費用(入院が必要な場合)、そして眼内レンズ代まで、全て保険適用となります。
これは最も一般的な白内障手術の形態で、多くの患者さんがこの方法で手術を受けています。
多焦点眼内レンズの保険適用状況
多焦点眼内レンズを使用する場合、2020年4月からは「選定療養」という制度が適用できるようになりました。これにより、手術費用の一部に保険が適用されるようになっています。
選定療養では、手術費用は保険適用となりますが、単焦点レンズとの差額分(多焦点レンズ代)は自己負担となります。具体的には、「多焦点レンズの費用」から「保険適用の単焦点レンズの費用」を差し引いた金額を自己負担する形です。
ただし、すべての医療機関が選定療養を導入しているわけではありません。導入していない医療機関では、多焦点レンズを使用した手術は完全な自由診療となり、手術費用もレンズ代も全額自己負担となります。
レーザー白内障手術の保険適用
近年注目されているレーザー白内障手術(FLACS)は、通常、保険適用外の自由診療となります。単焦点レンズを使用する場合でも、レーザーを使用する手術方法自体が保険適用外となるケースが一般的です。
ただし、2020年に医学誌『Lancet』で発表されたフランスの大規模研究によると、レーザー白内障手術と従来の超音波手術の術後3ヶ月の成績に有意な差はないことが判明しています。費用対効果を考えると、特殊なケース(角膜移植歴がある方、極度に硬い白内障、チン小帯脆弱症など)を除いて、保険適用の従来手術で十分な効果が期待できるケースも多いようです。

高額療養費制度の活用方法
白内障手術を受ける際、特に両目の手術が必要な場合は、高額療養費制度を活用することで自己負担額を大幅に抑えることができます。この制度をうまく利用するコツを紹介します。
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される制度です。
年齢・所得による自己負担限度額
高額療養費制度における自己負担限度額は、年齢と所得によって異なります。
70歳以上の方の場合:
- 1割負担の方 → 8,000円/月が上限
- 2割負担の方 → 18,000円/月が上限
- 3割負担の方(現役並み所得者) → 57,600円~252,600円+α/月が上限
70歳未満の方の場合:
- 年収370万~770万円の方 → 80,100円+(医療費-267,000円)×1%/月が上限
- 年収770万円以上の方 → 252,600円+(医療費-842,000円)×1%/月が上限
同月手術のメリット
白内障手術を両目行う場合、同じ月内に両目の手術を受けることで、高額療養費制度の恩恵を最大限に受けることができます。
例えば、70歳以上で1割負担の方が両目の手術を受ける場合、それぞれ別の月に手術すると、各月8,000円ずつ、合計16,000円の負担となります。しかし、同じ月に両目の手術を行えば、月の上限額8,000円で済みます。
このように、同月内に手術をスケジュールすることで、負担額を半分に抑えることも可能です。
限度額適用認定証の活用
高額療養費制度をさらに便利に利用するには、事前に「限度額適用認定証」を取得しておくことをお勧めします。
この認定証を医療機関の窓口で提示すると、その場での支払いが自己負担限度額までで済みます。認定証がない場合は、いったん医療費の全額を支払い、後日申請して払い戻しを受ける形になります。
限度額適用認定証は、加入している健康保険の窓口(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口など)で申請できます。手術の予定が決まったら、早めに申請しておくとよいでしょう。
医療費控除を活用した費用負担の軽減
白内障手術の費用負担を軽減するもう一つの方法として、医療費控除の活用があります。特に多焦点レンズを使用した自由診療の場合は、高額な費用がかかるため、医療費控除の恩恵が大きくなります。
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税の一部が還付される制度です。
医療費控除の対象となる費用
白内障手術に関連して、医療費控除の対象となる主な費用は以下の通りです。
- 診察料・検査料
- 手術費用
- 入院費用(差額ベッド代は対象外)
- 処方薬の費用
- 通院のための交通費
保険適用の手術だけでなく、自由診療の多焦点レンズを使用した手術費用も医療費控除の対象となります。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算式は以下の通りです。
医療費控除額 = 支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填された金額 – 10万円(または所得の5%のいずれか少ない方)
例えば、年間の医療費が50万円で、保険金などの補填がなく、所得が400万円の場合:
- 10万円と所得の5%(20万円)のうち少ない方は10万円
- 医療費控除額 = 50万円 – 0円 – 10万円 = 40万円
この40万円が課税所得から差し引かれることになります。所得税率が20%の場合、40万円×20% = 8万円が還付される計算になります。
確定申告の方法と必要書類
医療費控除を受けるには、翌年の2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行う必要があります。
必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書(医療費控除の明細書を含む)
- 医療費の領収書(申告時の提出は不要ですが、5年間保管が必要)
- 源泉徴収票
近年は、医療費の領収書の提出は不要となり、「医療費控除の明細書」の提出で済むようになりました。ただし、税務署から求められた場合に備えて、領収書は5年間保管しておく必要があります。
民間保険の活用と給付金
白内障手術の費用負担を軽減する方法として、公的制度だけでなく民間の医療保険も有効活用できます。特に医療保険や生命保険の特約として付いている手術給付金は、白内障手術でも受け取れる可能性があります。
すでに加入している保険がある方は、白内障手術が給付対象になるかどうか確認してみましょう。
手術給付金の対象となる条件
白内障手術が手術給付金の対象となるかどうかは、保険会社や契約内容によって異なります。一般的には、以下の条件を満たす場合に給付対象となります。
- 公的医療保険が適用される手術であること
- 契約している保険の「手術給付金」の対象手術に含まれていること
多くの医療保険では、公的医療保険の対象となる手術であれば給付対象となりますので、単焦点レンズを使用した保険適用の白内障手術は、給付対象になる可能性が高いです。
給付金の申請方法
手術給付金を受け取るためには、以下の手順で申請を行います。
- 保険会社に連絡し、給付金請求の手続きを確認する
- 医療機関で「診断書」や「手術証明書」を取得する
- 保険会社指定の「給付金請求書」に必要事項を記入する
- 必要書類を揃えて保険会社に提出する
診断書や手術証明書の取得には費用がかかりますが、多くの保険会社では、入院や手術の事実が確認できる書類(領収書や明細書など)でも代用できる場合があります。事前に保険会社に確認しておくとよいでしょう。
両目手術の注意点
白内障手術を両目行う場合、手術給付金に関して注意すべき点があります。
多くの保険では、「同一の手術を複数回受けた場合」の給付に制限があります。例えば、「同じ手術を60日以内に受けた場合は1回分のみ給付」といった条件がある場合、両目の手術を短期間で行うと、片目分の給付しか受けられないことがあります。
このような制限がある場合は、両目の手術の間隔を保険の規定に合わせて調整するか、あるいは高額療養費制度の恩恵を優先して同月内に手術を行うかを検討する必要があります。保険の契約内容をよく確認し、最適な選択をしましょう。

費用を抑えるための具体的な方法
白内障手術の費用を抑えるためには、いくつかの具体的な方法があります。ここでは、実際に費用を抑えるための戦略をご紹介します。
費用面での不安を解消し、安心して手術を受けるための参考にしてください。
手術時期の最適化
白内障手術の費用を抑えるためには、手術時期の調整が重要です。
- 両目の手術が必要な場合は、同じ月内に行うことで高額療養費制度の恩恵を最大限に受けられます
- 年末に手術を予定している場合は、翌年初めに延期することで、医療費控除を2年分申請できる可能性があります
- 医療費が多くかかる他の治療と同じ年に集中させることで、医療費控除の恩恵を大きくすることができます
ただし、白内障が進行して日常生活に支障をきたしている場合は、費用面だけでなく視力回復の緊急性も考慮して判断する必要があります。
医療機関の選択
医療機関によって、白内障手術の費用や対応が異なります。費用面を考慮した医療機関選びのポイントは以下の通りです。
- 保険適用の単焦点レンズでの手術を基本としている医療機関を選ぶ
- 多焦点レンズを希望する場合は、選定療養を導入している医療機関を選ぶ
- 診察から手術までの通院回数が少ない医療機関を選ぶ(交通費の節約)
- 日帰り手術に対応している医療機関を選ぶ(入院費の節約)
当院では、患者さんのニーズに合わせた多様な選択肢を提供しています。保険適用の単焦点レンズから多焦点レンズまで、様々なタイプのレンズを取り扱っており、患者さんの視力状態や生活スタイル、経済状況に合わせた最適な提案を心がけています。
公的助成制度の活用
自治体によっては、白内障手術に対する独自の助成制度を設けている場合があります。特に高齢者や低所得者向けの医療費助成制度は、白内障手術の費用負担軽減に役立つことがあります。
お住まいの自治体の福祉課や保健センターに問い合わせて、利用できる助成制度がないか確認してみるとよいでしょう。
また、身体障害者手帳をお持ちの方は、自立支援医療(更生医療)の対象となる場合があります。この制度を利用すると、医療費の自己負担が軽減される可能性があります。
まとめ:最適な白内障手術選択のために
白内障手術の費用相場と保険適用の仕組みについて詳しく解説してきました。最後に、これまでの内容をまとめ、最適な選択をするためのポイントを整理します。
白内障手術は、適切な知識と準備があれば、経済的な負担を最小限に抑えながら受けることができます。
費用面から見た選択肢の比較
白内障手術の主な選択肢を費用面から比較すると、以下のようになります。
- 単焦点レンズ(保険適用):最も費用負担が少なく、高額療養費制度も利用可能。ただし、術後も状況によっては眼鏡が必要。
- 多焦点レンズ(選定療養):手術費用の一部に保険が適用され、完全自由診療よりは負担が軽減。遠近両用の見え方が得られるメリットがある。
- 多焦点レンズ(自由診療):費用負担は最も大きいが、医療費控除で一部還付の可能性あり。遠近両用の見え方が得られるメリットがある。
どの選択肢が最適かは、ご自身の視力状態、生活スタイル、経済状況によって異なります。眼科医とよく相談して決めることをお勧めします。
費用負担を軽減するための3つのポイント
白内障手術の費用負担を軽減するための重要なポイントは以下の3つです。
- 高額療養費制度の活用:両目の手術は同じ月に行い、事前に限度額適用認定証を取得しておく
- 医療費控除の申請:年間の医療費をまとめて確定申告し、所得税の一部還付を受ける
- 民間保険の給付金確認:加入している医療保険や生命保険の手術給付金が適用されるか確認する
これらの制度をうまく活用することで、白内障手術の実質的な自己負担額を大幅に抑えることができます。
最後に:安心して手術を受けるために
白内障は放置すると視力低下が進行し、日常生活の質を大きく低下させます。費用面での不安から手術を躊躇されている方も多いかもしれませんが、適切な情報と準備があれば、経済的な負担を最小限に抑えながら手術を受けることが可能です。
当院では、患者さん一人ひとりの状況に合わせた最適な治療プランをご提案しています。白内障手術をお考えの方は、まずは無料相談にお越しください。費用面のご不安も含めて、丁寧にご説明いたします。
目の健康は、生活の質を大きく左右します。適切な時期に適切な治療を受けることで、明るく快適な毎日を取り戻しましょう。
詳しい情報や無料相談のご予約は、南船橋眼科までお気軽にお問い合わせください。
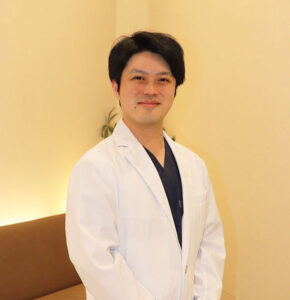
経歴
- 筑波大学医学群医学類 卒業
- 東京都立多摩総合医療センター 臨床研修医
- 東京医科歯科大学医学部附属病院 眼科
- 東京都保健医療公社大久保病院 眼科
- 川口市立医療センター 眼科
- 川口工業総合病院 眼科
- 柏厚生総合病院 眼科
- 南船橋眼科 院長








